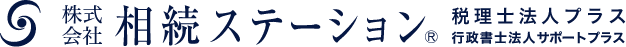遺贈寄付とは?必要な遺言書の作り方やメリットを解説!
遺言によって遺産の一部あるいは全部を公益団体などに寄付することを「遺贈寄付」といいます。
遺贈寄付は、ご自身の財産を公益に役立てることができるうえ、相続税の節税対策としても有効です。
そのため近年関心が高まっていますが、相続人以外に遺産を譲る遺贈についてわからないことが多く踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、遺贈のメリットや注意点、遺贈寄付の方法についてわかりやすく解説します。
遺贈とは?かかる税金や遺贈のメリットについて

遺贈とは、遺産の行く先を決める方法のひとつで、遺言書によって財産の一部あるいは全部の譲り先を指定することです。
相続では相続人以外に遺産を譲ることはできませんが、遺贈では相続人以外の個人や法人を指定することができます。
まずは、遺贈の仕組みについてご説明しましょう。
遺贈で相続人以外にも遺産を譲る
遺言書を作成せずに亡くなった場合、故人(被相続人)の所有財産は遺産として相続人に渡ります。
このときの相続人とは、被相続人の配偶者や子どもです。
子どもがいない場合は父母、父母もいない場合は兄弟姉妹と範囲は広がりますが、親族以外は相続人に含まれません。
しかし、遺贈を選択すれば、相続人だけでなく相続人以外の個人や法人にも財産を譲ることができるというわけです。
相続人以外の個人
相続人として認められる配偶者は、戸籍上の正式な婚姻関係を結んだ相手を指します。
内縁関係や事実婚パートナー、同性パートナーなどは、遺言書による遺贈でなければ財産を受け取ることができません。
また、お世話になった人や事業パートナーなど特定の他人に遺贈することもできるため、最後に謝意を伝えたいという思いを叶えることができます。
団体や法人
遺贈先には、特定の企業や団体、国や自治体なども選択可能です。
病院や教育機関、文化芸術振興事業、子育てサポートや国際協力、災害支援活動や動物保護など、様々なNPO法人や公益団体などに「遺贈寄付」をすることもできます。
遺贈によるメリット・デメリット
遺贈によるメリットとデメリットは、どのようなものがあるでしょうか。
遺贈のメリット
最大のメリットは、通常の相続では相続人に含まれない相手にも財産を残せるということでしょう。
人生の最後に残ったお金を思い通りに処分できる充足感も見逃せない利点です。
また、遺贈のシステムを上手く利用することで、事前に予想される遺産トラブルが回避できるケースもあるのではないでしょうか。
遺贈のデメリット
一方で、遺贈のデメリットは、本来の相続人の心情を害しやすいということです。
相続人にとって不本意な相手が遺産を受け取ったり、遺贈割合によっては相続人の取得分が減ってしまったりと、不安や不満を抱く可能性が高いでしょう。
また、各相続人には民法によって最低限の取得額が保証されており、実際の取得額が保証額を下回った場合は遺贈を受け取った人(受贈者)に差額を請求する権利があります。
もめごとの種を蒔くおそれもあることを知っておきましょう。
また、被相続人の遺産総額や遺贈内容によっては、受遺者に相応の税金が課税されるという点にも注意が必要です。
遺贈で得た相続税の計算方法と注意点

生前におこなわれる贈与は「贈与税」の対象ですが、死亡をきっかけにおこなわれる遺贈は「相続税」の対象となります。
では、基本的な相続税の計算方法について、流れに沿って簡単に説明しましょう。
①課税遺産総額の計算
相続税は、遺産のすべてにかかるわけではありません。
遺産総額が一定金額以上あった場合に、ボーダーラインを上回った部分のみが課税対象となります。
まずは、次の手順で「課税遺産総額」を算出します。
相続人数と基礎控除の確認
相続税における課税のボーダーラインは、「基礎控除額を超えるかどうか」です。
基礎控除額を算出するためには、下記の計算式を使います。
| 基礎控除額:3000万円+(法定相続人数×600万円) |
法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。
下記の通りに範囲や順序が決まっています。
●配偶者
配偶者は、常に相続人です。
その他の親族がいる場合は、配偶者と共に相続人となります。
●配偶者以外の親族
・第1順位:被相続人の子ども(子どもが亡くなっている場合は、孫、ひ孫)
・第2順位:被相続人の父母(父母が亡くなっている場合は、祖父母、曾祖父母)
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪)
遺産と債務の確認
相続税は、遺産総額のうち基礎控除額を超過した部分にのみかかります。
遺産には、金融資産や不動産、宝石貴金属といった金品を得る権利「=プラスの財産」と、被相続人の借入金や未払金といった債務を返済する義務「=マイナスの財産」が含まれます。
遺産の把握には一覧や目録を作成し、時価による評価額を求めておくことが重要です。
| 課税遺産額:(プラスの財産-マイナスの財産)-基礎控除額 |
上記の計算をおこない課税遺産総額が0円以下だった場合、相続税はかかりません。
課税遺産額がいくらかある場合は、次のステップ「相続税の計算」へと進みます。
②全体の相続税額の計算
ここからは、課税遺産額に対する相続税額の計算です。
| 法定相続分による相続税額:課税遺産額×法定相続分割合×相続税率-控除額 ※相続人数分 |
●法定相続分
法定相続分は民法によって定められた遺産取得割合で、相続人の組み合わせによって下記のように異なります。
・配偶者と子ども:配偶者1/2、子1/2
・配偶者と父母:配偶者2/3、父母1/3
・配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
●相続税の速算表
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1000万円以下 | 10% | - |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
次に、各自の「法定相続分による相続税額」を合計して、「全体の相続税額」を算出しましょう。
| 全体の相続税額:法定相続分による相続税額の合計 |
③遺言の執行と遺産分割
遺産分割を終えたら、次におこなうのは実際の取得額に応じた相続税額の計算です。
| 実際の相続税額:遺産取得額/課税遺産額×全体の相続税額 ※遺産を取得した人数分 |
このとき、遺贈によって遺産を取得した受遺者も同様に計算をおこないます。
控除や特例の適用
最後に、税額軽減の控除制度や特例で要件を満たすものを適用します。
主な控除には「配偶者控除」「未成年控除」「障がい者控除」などがあり、相続人を対象としているものがほとんどです。
個人へ遺贈する場合の注意点
ここまでの手順は、「相続人の納める相続税計算」となります。
相続人以外の受遺者は、もう1ステップ進みましょう。
相続税2割増し
「被相続人の配偶者や一親等血族」が遺産を取得した場合、相続税額は2割増しとなります。
ここまでの基本的な相続税計算で割り出した相続税額に1.2をかけた金額が、実際の納税額です。
不動産関連税
受遺者が取得した遺産に土地や家屋などの不動産が含まれている場合、相続税とは別に次の税金がかかります。
・不動産取得税:固定資産税評価額×4%(不動産を取得した場合)
・登録免許税:固定資産税評価額×2%(取得した不動産の所有権移転登記をおこなった場合)
団体・法人へ遺贈する場合の注意点
遺贈先が団体や法人だった場合は、事業内容によって課税状況が異なるため注意が必要です。
●普通法人は法人税がかかる
収益事業をおこなう団体や法人は、普通法人としてすべての所得に法人税が課税されます。
遺贈で取得した財産も法人税の対象です。
●公益法人は非課税
自治体や教育、宗教、慈善、美術館など非営利の公益事業をおこなう団体や組織、法人が遺産を取得した場合、原則として税金はかかりません。
つまり、公益法人を対象としておこなう遺贈寄付は非課税でおこなえるというわけです。
3つの遺贈寄付「遺言」「相続財産」「生命保険・信託」 を詳しく解説

近年、遺贈寄付についての相談が増えています。
「生きているうちは私たちの生活費の確保で余裕がなかったけれど、死後は子どもたちの未来を考えて社会に貢献したい」という方に知っていただきたいのが遺贈寄付という選択です。
公益法人に遺贈寄付をおこなう場合は、次の3つの方法が考えられます。
遺言による遺贈寄付
被相続人が生前に遺言書を作成し、死後にその意思に従って遺贈寄付をおこなう方法です。
遺族や遺言執行者が間違いなく実行できるように、遺贈寄付先の情報や遺贈寄付の方法、アクセス手段などを明確にしておきましょう。
ただし、団体や法人によっては、寄付を受け付けていない場合や「現金のみ」といった制限が設けられている場合もあります。
事前に寄付を検討している団体・法人に連絡をとり、寄付についての方針を確認しておくと安心です。
包括遺贈と特定遺贈
遺言による遺贈には、「遺産総額の割合を指定する包括遺贈」と「特定の金品を指定する特定遺贈」があります。
例えば「遺産総額の3割を遺贈」と指定された包括遺贈の場合は、実際にどのように遺産分割をおこなうのか相続人全員で協議をしなくてはなりません。
遺贈寄付の場合は「現金500万円」など、何をどうすればよいのかわかりやすい特定遺贈を選ぶ方がよいでしょう。
相続財産による遺贈寄付
相続財産による遺贈寄付とは、いったん相続人が受け取った財産を寄付することをいいます。
前もって、遺産を受け取る人に「寄付したい」ということを伝えておくと流れがスムーズでしょう。
ただし、遺言書のような強制力はないため、実現するかどうかは相続人に委ねられることになります。
生命保険信託による遺贈寄付
一般的な生命保険では、原則として、死亡保険金の受取人に配偶者や二親等以内の親族(子・親)以外を指定することができません。
内縁関係や事実婚パートナーが受取人として認められるケースはありますが、まったくの他人や法人を指定できるものはまずないでしょう。
遺贈寄付を考えている場合は、「生命保険」ではなく「生命保険信託」を利用します。
生命保険信託の概要
生命保険信託は、一部の保険会社や信託銀行で取り扱っている保険商品です。
生命保険信託では、保険契約者(委託者)が生前に死亡保険金の活用方法を設計し、信託銀行(受託者)と信託契約を結びます。
万一の場合は、信託銀行が死亡保険金を受け取り、指定通りに支払うというしくみです。
主に、受取人(受益者)が未成年・高齢者・障がい者などで財産管理が難しいケースに用いられますが、公益団体への寄付を指定することもできます。
遺贈の際には節税対策が必要?

これから遺贈や遺贈寄付を検討している人の中には、節税対策としておこないたいという人もいるのではないでしょうか。
そこで、ここからは遺贈と併せて考えておきたい節税対策について案内します。
相続税がかからないケース
相続税計算の項でも説明しましたが、相続税は「基礎控除額を超過した部分のみ」に課税される税金です。
つまり、基礎控除額を上回る部分をできるだけ減らすことが、将来の相続税額を減らすことに繋がります。
では、具体的な方法について見ていきましょう。
生前中の寄付
自治体や公益法人などに生前中に寄付した場合は、死亡時の遺産額が既に減っているので、当然相続税も節税になります。
どうせ財産の一部を寄付するなら、遺贈寄付ではなく、生前寄付も一考の価値はあります。
生前贈与による節税対策
亡くなった後に遺産相続させるのではなく、生前から財産を贈与しておくという方法です。
贈与相手や目的に応じて、いくつかの方法があります。
暦年贈与
贈与税の基礎控除は、「毎年110万円」です。
つまり、年間110万円以内の贈与には贈与税はかかりません。
そこで、将来的に遺贈したいと思っている相手に、基礎控除枠内の贈与を繰り返すという方法があります。
1年あたりは110万円ですが、続けることで贈与額は大きくなり、その分相続財産額を減らすことができるというわけです。
また、贈与税の基礎控除は贈与を受ける相手が親族以外でも適用されます。
特に相続税が2割増しになってしまう相続人以外への遺贈を考えている人には、効果的な節税対策となるでしょう。
一括贈与
配偶者や子ども、孫などの直系卑属に遺贈を予定している場合は、贈与の目的ごとに非課税枠が設けられた一括贈与を利用するのも良いでしょう。
●夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産取得費用の贈与がおこなわれた場合、基礎控除の他に最高2000万円まで非課税となります。
贈与によって取得した居住用不動産に実際に居住することが、要件の1ひとつです。
また、同じ配偶者からの贈与については、控除適用は一生に一度しか受けられません。
●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
父母や祖父母など直系尊属から、居住用家屋の新築・取得・増改築の対価を贈与された場合、要件を満たすことで一定の額が非課税となる制度です。
非課税限度額は最高1000万円で、住宅の種類や耐熱・耐震等級等によって異なります。
●直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
30歳未満の子や孫が、祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、1500万円までが非課税となる制度です。
ただし、入学金や授業料、学用品購入費、塾や習い事費用など、学校や教育機関に直接支払われるものに使途が限られます。
●直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
18~50歳未満の子や孫が、父母や祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、1000万円までは非課税となる制度です。
結婚・子育て資金とは、結婚式費用、新居費用、出産費用、不妊治療費用、子の医療費、保育料などが該当します。
生前贈与の注意点
非課税でおこなえる生前贈与を紹介しましたが、次の点には注意が必要です。
●「定期贈与」の指摘
暦年贈与では、「同一人物から、毎年同時期に、同額の贈与がある」場合、税務署に「定期贈与」を疑われる可能性があります。
「最初から大金を贈与する意図で定期贈与をおこなっている」と判断された場合は、税務調査がおこなわれるかもしれません。
その都度贈与の契約書をつくる、贈与額を変える、時期をずらすなどの工夫が必要です。
●死亡前3年以内の贈与財産
被相続人が亡くなる3年以内(令和6年(2024年)以降の贈与は税制改正により4年~7年以内)に贈与された財産は、相続税の課税対象です。
このとき、基礎控除額110万円以下の暦年贈与も相続税の課税遺産額として加算することになります。
ただし、一括贈与のうち非課税の適用を受けた額は加算されません。
又、令和6年(2024年)以降の贈与について相続時精算課税贈与制度を選択すれば、税制改正により相続発生前3年~7年以内の贈与であっても1人110万円以下の贈与までは相続税の課税遺産額に加算されません。
遺贈をおこなう際の遺言書作成はプロにお任せください

遺贈や遺贈寄付をおこなうために確実な方法は、遺言書を作成することです。
しかし、遺言書には厳密な形式が定められており、形式不備の場合は効力を発揮することができません。
また、税の負担や相続人の心情など、多様な視点から遺贈先についても慎重に検討する必要があるでしょう。
形式不備や無効リスクのない遺言書の作成は、専門知識を備えたプロにお任せいただくと安心です。
法律だけでなく税務にも詳しい税理士ならば、効果的な節税対策についての相談にも対応できます。
まずは、関連リンクから遺贈や節税対策の相談実績などをご覧ください。
無料相談サービスなどを利用して、気軽にご質問いただくのも歓迎です。
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計2,950件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続税申告
トータルサポート
このサポートを詳しく見る

土地評価の実務
このサポートを詳しく見る

遺産分割サポート
このサポートを詳しく見る

税務調査対策
このサポートを詳しく見る

書類取得の代行
(遺産整理・遺言執行)
このサポートを詳しく見る

不動産相続、
農地・生産緑地承継、
不動産の売却
このサポートを詳しく見る

その他の相続税
・相続の関連項目
このサポートを詳しく見る
相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。